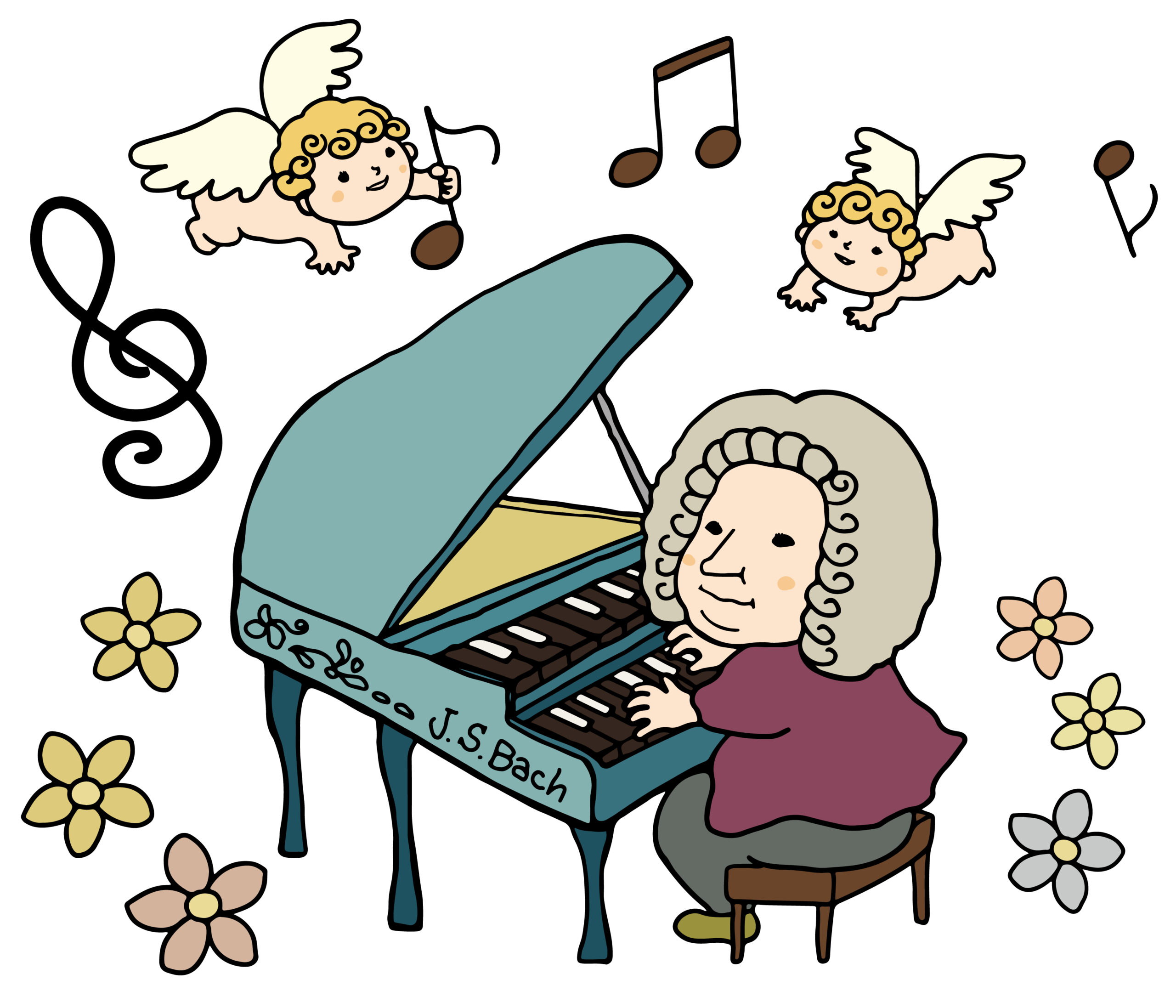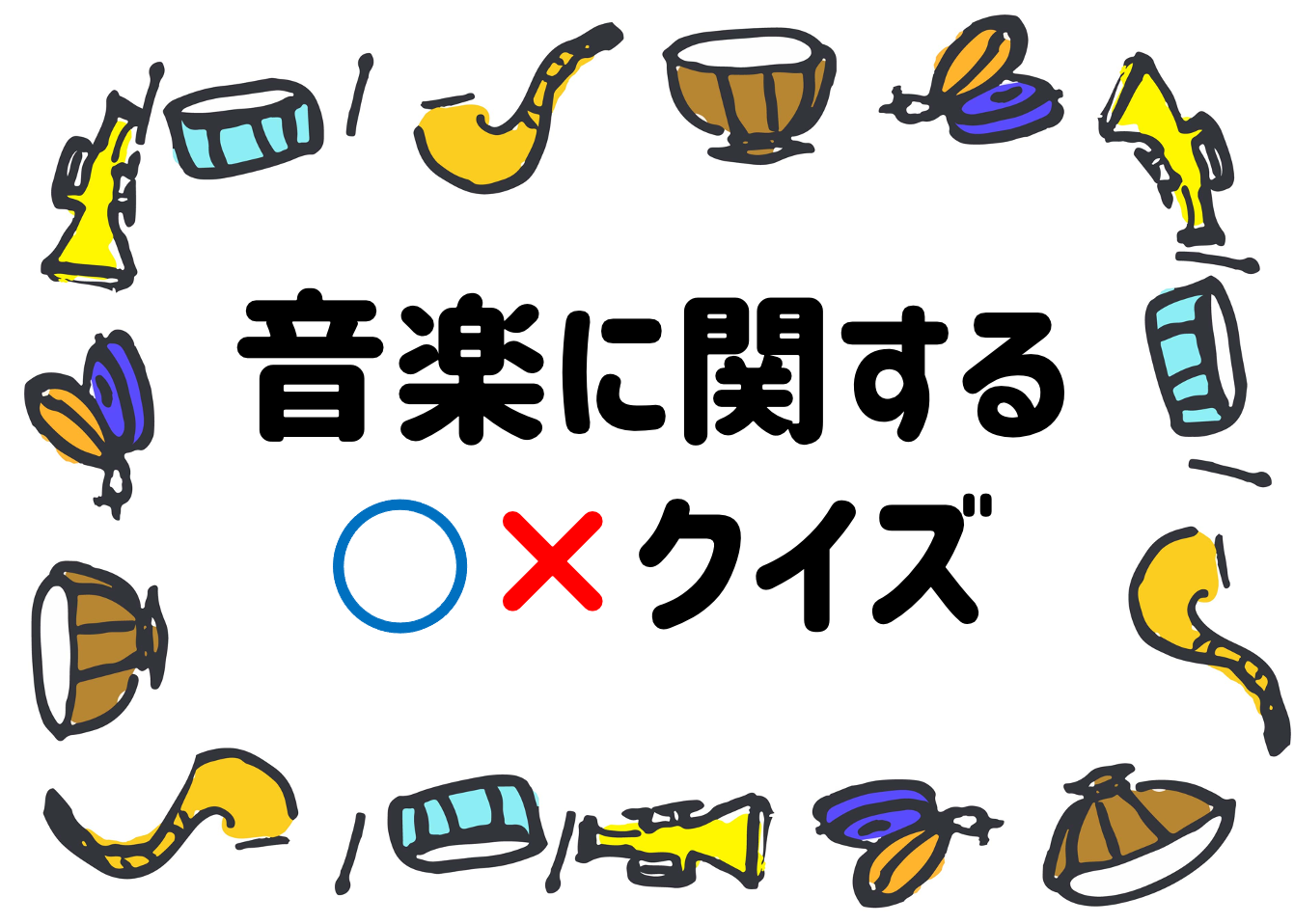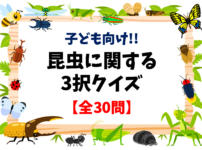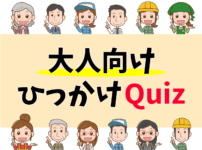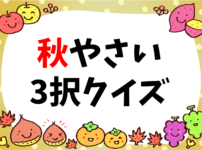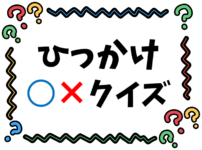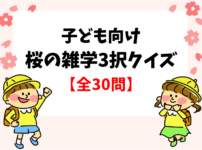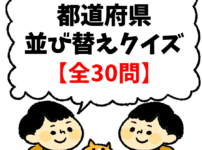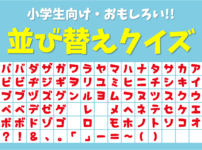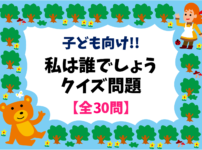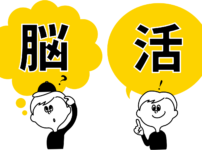王様
今回は音楽に関する○×クイズを出題するぞ!全問正解目指して頑張るのじゃ。
【中学生向け】音楽に関する雑学!知識を問う盛うマルバツクイズ問題【前編10問】
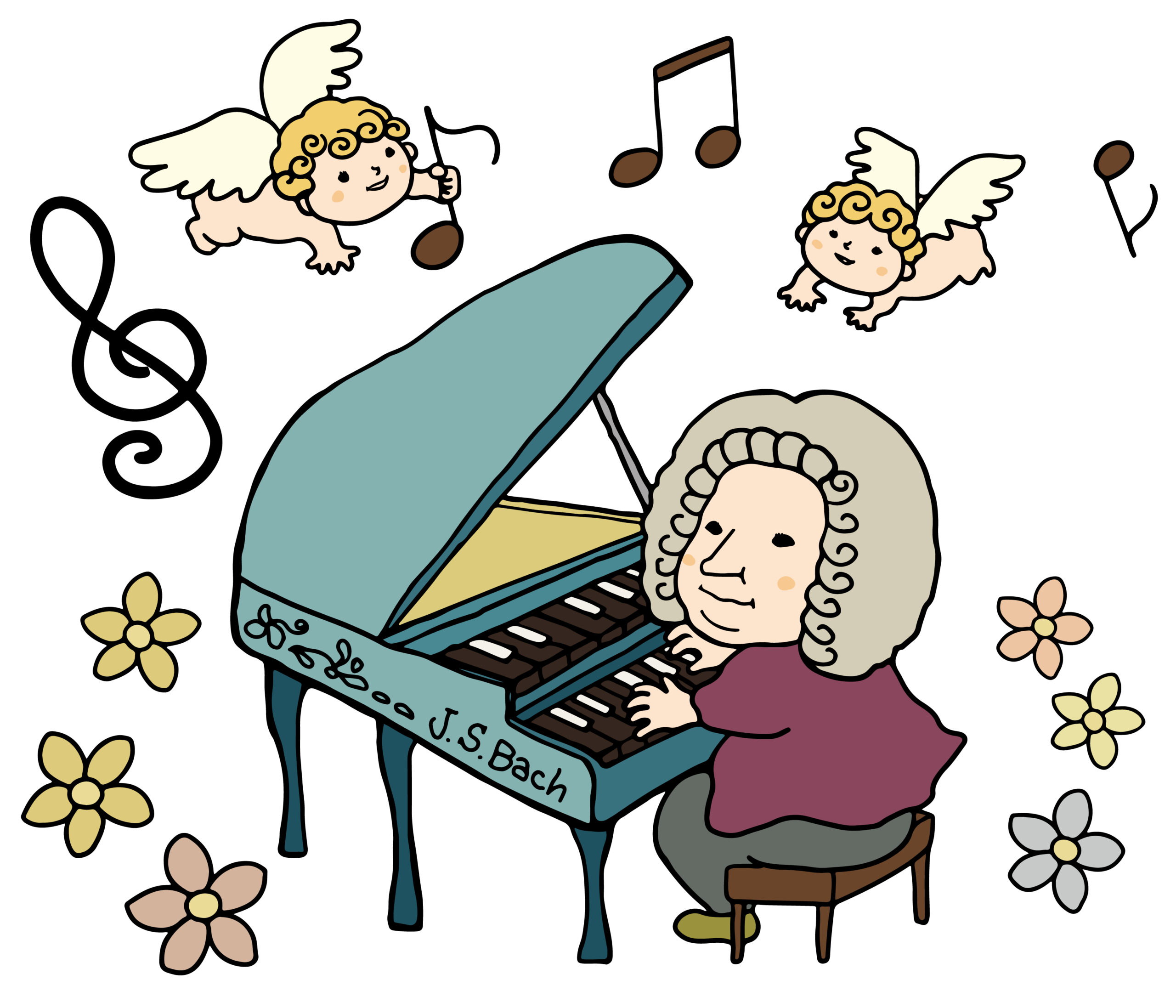

王様
まずは10問出題するぞぉ!〇か×か、正解だと思う方を選ぶのじゃ。
第1問
「音楽の父」と言われる人物は「バッハ」である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
バッハは、西洋音楽の基礎を作ったと言われる作曲家です。
そんなバッハが「音楽の父」と言われている理由は、「機能和声理論(きのうわせいりろん)」という理論を構築したからです。
この理論は、たとえばJ-popや洋楽・アニソンなど、現代の音楽には欠かせない土台・基礎となる考え方です。
しかし、バッハに対する評価は生きているうちは高くはなく、評価されるようになったのはバッハが亡くなった後からでした。
第2問
日本で初めてカラオケ店が登場したのは、「沖縄県」である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
日本初のカラオケボックスは1985年、岡山県岡山市に登場しました。
当時は今みたいな個室作りのおしゃれな感じではなく、船に積むコンテナを改造して作られたものでした。
第3問
「猫ふんじゃった」は、現在も誰が作った曲か分かっていない。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
「猫ふんじゃった」は、軽快なメロディーが耳に残りやすく比較的、日本では有名な曲ですが、この曲は今現在も、どこの誰が作ったか分からないと言われています。
また、日本以外にも世界中で聴かれており曲の名前が国によって異なります。
日本は「猫ふんじゃった」ですが、中国は「泥棒行進曲」ハンガリーは「ロバのマーチ」、ロシアでは「犬のワルツ」、ドイツでは「ノミのワルツ」という名前だそうです。
第4問
クラッシックとは「元気が出る」という意味である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
「クラシック音楽」とは主に17世紀から19世紀頃にかけ、バッハやモーツアルトなど有名な音楽家たちが残した音楽を指します。
語源は「class(クラス)=階級」が由来で、「一流」や「最高クラス」といった意味でした。そして、そこから派生し「格式のある」という意味になったと言われています。
第5問
「ドレミファソラシド」は日本の言葉である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
ドレミファソラシドは、元はイタリア語です。
世界共通で同じ音ですが、国によって呼び方が変わります。
例えば、英語の場合は「CDEFGABC」、つまり日本で言うとドがCになります。また、日本は昔「イロハニホヘト」といった音の表し方がありました。
第6問
最後まで聞き終わるのに1000年かかる曲がある。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
この曲は、イギリスのミュージシャン・ジェム・ファイナーさんが作曲しました。
20分20秒の長さの1曲がベースとなっており、全てを演奏し終えるまでに1000年かかる計算になっています。
2000年1月1日からスタートし、終了予定は2999年12月31日となっています。
第7問
学校などで使用するカスタネットは赤と青ですが、この配色になった理由は未だにわかっていない。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
赤と青の2色になっている理由は、赤は女子、青は男子の色として男女兼用にするためです。
1つで2色を使用することによって、単色でそれぞれ用意するよりも、生産や在庫管理が楽となり現在の形になりました。
第8問
ウクレレの弦は全部で10本である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
ウクレレの弦は、全部で4本です。
ウクレレの発祥はポルトガル移民が持ち込んだ「ブラギーニャ」という楽器と言われています。
ちなみに、ウクレレは弾く際に指が高速で動く様子をノミに例え、ハワイ語で「飛び跳ねるノミ」という意味があります。
第9問
「君が代」の歌詞にある「さざれ石」のモデルは首都・東京に存在する。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
「さざれ石」は漢字で書くと「細石(小石のこと)」と書きます。
「さざれ石」は、岐阜県の揖斐川町にあります、
その周辺は「さざれ石公園」として管理されており、岐阜県の天然記念物にも指定されています。
その後の歌詞にある「巌(いわお)となりて」は、たくさんの小石が長い時間をかけて大きな岩になりました、という意味を表しています。
第10問
昔の指揮者は鉄の棒を振っていた。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
答えは、杖です。
17世紀の初めから18世紀半ば頃の指揮者は、杖を地面に打ち付けることでテンポをとり、指揮をとっていました。
指揮棒が主流の現在でも、マーチングでは指揮杖が使用されています。
【中学生向け】音楽に関する雑学!知識を問う盛うマルバツクイズ問題【中編10問】


王様
前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
管(かん)・弦(げん)・打(だ)楽器で演奏される「合奏の形」をオーケストラという。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
「オーケストラ」という言葉は、ギリシャ語の「オルケーストラ」に由来し、舞台と観客席の間の半円形のスペースを指しています。
第12問
管楽器トロンボーンは男性の声の最も近しいと言われている。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
トロンボーンはイタリア語のトランペット「tromba(トロンバ)」に、「大きい」という接尾語を付けて出来上がった言葉です。
そんなトロンボーンの音は一般的な男性の声とほぼ同じ音域とされています。
第13問
バイオリンを漢字で書くと「風琴(ふうきん)」である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
バイオリンは漢字で書くと「提琴(ていきん)」と書きます。
「風琴(ふうきん)」はオルガンの事を指します。
ちなみに、バイオリンは高いもので10億円以上し、それは主に17~18世紀に造られたバイオリンが多く高額な価値を生み出しています。
第14問
CDに録音可能な最大時間は74分42秒である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
CDに録音できる最大時間は74分42秒です。
それ以上は絶対的に長く録音することはできません。
CDが発売されたのが1982年で、オランダのフィリップスという会社と日本のソニーとの共同開発でした。
第15問
ドレミには色がある。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
音から一定の色を感じることが出来ることを「共感音(きょうかんおん)」と言い、その感じた色に明確に色覚があることを色聴(しきちょう)と言います。
ちなみに、音階のドレミは以下のような色に見えるそうです。
【例】「ド」:赤 「レ」:すみれ色 「ミ」:黄金色
第16問
年齢が高くなるにつれ聞こえない音がでてくる。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
「モスキート音」という音は、年を重ねると聞こえなくなっていく音です。
モスキート音とは、蚊が飛んでいる時のようなキーンとする高音のことです。
この音が聞こえる若者にとっては不快な音なので、それを利用してコンビニの入り口や若者が意味もなくたむろしてしまう場所にモスキート音を流して対策することもあります。
第17問
世界一短い曲は、たった5秒で終わる。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
世界一短い使い歌は、イギリスのバンドが製作した「You Suffer(ユー サッファー)」という曲で、その演奏時間は「1秒」。ギネス記録にもなっています。
カラオケにも入っていて歌うことができます。
歌詞は「You Suffer But Why」(お前は苦しむ、しかし何故なのか? )のみです。
「苦しむことに意味はあるのか? 何に苦しむために俺たちは作られたのだろうか?」という「不条理な世界、世の中に対するアンチの曲」だそうです。
第18問
昔のピアノは白と黒の位置が逆だった。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
諸説ありますが、バロック音楽の時代(1600年~1750年頃まで)のピアノは鍵盤の白い部分は、象の牙が使われていました。
しかし象の牙が高価だったため、面積が狭く数が少ない現在の黒い部分(シャープやフラット)の部分に使用するように変更したそうです。
第19問
盆踊りは江戸時代に生まれた。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
盆踊りの最古の記録は、室町時代です。
現在はお祭りの一環として催されている盆踊りですが、元々は亡くなった人を供養するための行事として全国に広まります。
明治時代頃からは娯楽の1つとしても親しまれ始めました。
第20問
原型を留めている形での残っている世界で最古い楽譜が発見されたのは日本である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
原型を留めている形での残っている世界で最古い楽譜はトルコで発見されています。
それは「セイキロスの墓碑銘(ぼひめい)」というもので、セイキロスという人のお墓に歌詞が書かれています。
歌詞は短く、現在の音符ではない古代ギリシアの音符が記載されており、セイキロスが妻に書いた曲であると言われています。
【中学生向け】音楽に関する雑学!知識を問う盛うマルバツクイズ問題【後編10問】


王様
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
世界一難しい木管楽器としてギネス認定されているのは、オーボエである。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
オーボエは、構造が複雑で演奏が難しい楽器です。
その難しさはギネス認定までされるほどです。
第22問
合唱のパートは全部で6種類ある。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
合唱のパートは6種類に分類されています。
女性はソプラノ、メゾ・ソプラノ、アルトの3つです。
男性はテノール、バリトン、バスの3つです。
第23問
「アカペラ」の語源はドイツ語である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
伴奏がない状態で歌うことを「アカペラ」と言います。
アカペラの語源は、イタリア語の「a cappella(聖堂で)」です。
第24問
大晦日恒例の紅白歌合戦は、最初はラジオ番組として始まった。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
紅白歌合戦は、1951年(昭和26年)にお正月のラジオ番組として始まりました。
その頃はまだテレビの放送自体が始まっていませんでした。
1953年(昭和28)にテレビの放送が始まったことで、同年の第4回放送から大晦日のテレビ番組としてスタートしました。
第25問
CDの売り上げ枚数は、年々増えてきている。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
少し前までは音楽を聴く手段としてはCDを買うのが一般的でしたが、現在は音楽をダウンロード購入したり、有料配信サービスで聴いたりと音楽に手軽に触れることができる手段が広まりました。
それにより、CDの売り上げ枚数は減ってきています。
第26問
サブスクで配信されている音楽は、お金さえ払っていれば永久的に聴くことができる。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
料金を払えば音楽が聴き放題になる便利なサブスクですが、欠点もあります。
それは今日まで聴けていた音楽が、明日突然聴けなくなる可能性があることです。
何らかの事情で曲の配信が停止されたり、サブスク自体のサービスが終了してしまうこともあります。
便利な反面、そのようなデメリットもあるということですね。
第27問
「クインテット」とは、4人で演奏することである。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:×
クインテットは5人で演奏することです。
4人で演奏するのは「カルテット」です。
第28問
「アンコール」の語源はフランス語である。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
演奏者や歌手が予定のとおり終了し退場したあと、聴衆が拍手や掛け声で再演を望むことを「アンコール」と言います。
語源はフランス語で、「再び。もう一度」という意味の言葉です。
第29問
歌詞のない国家を持っている国がある。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
イタリア半島の中東部に位置するサンマリノなど、歌詞がない曲だけの国歌を持っている国もあります。そのような国は世界的に見ても珍しいようです。
第30問
ギターには「ネック」と呼ばれる部分がある。〇か×か?
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:○
ギターやベース等の弦が張ってある細長い部分のことを「ネック」と呼びます。
強い衝撃を与えると折れてしまうこともあるため注意が必要です。

王様
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
「クイズ王国」ではいろんなクイズを紹介しているから、他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!