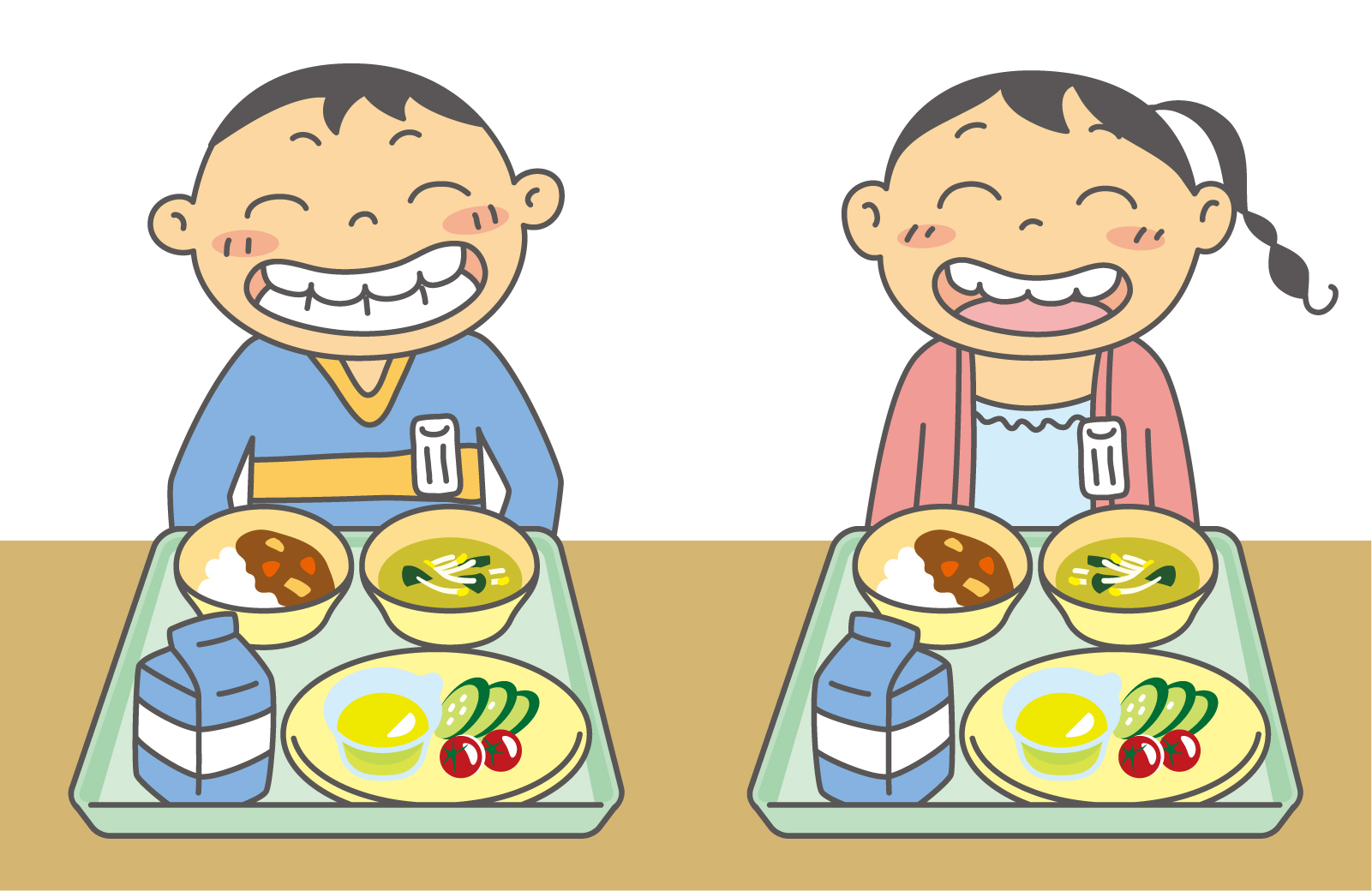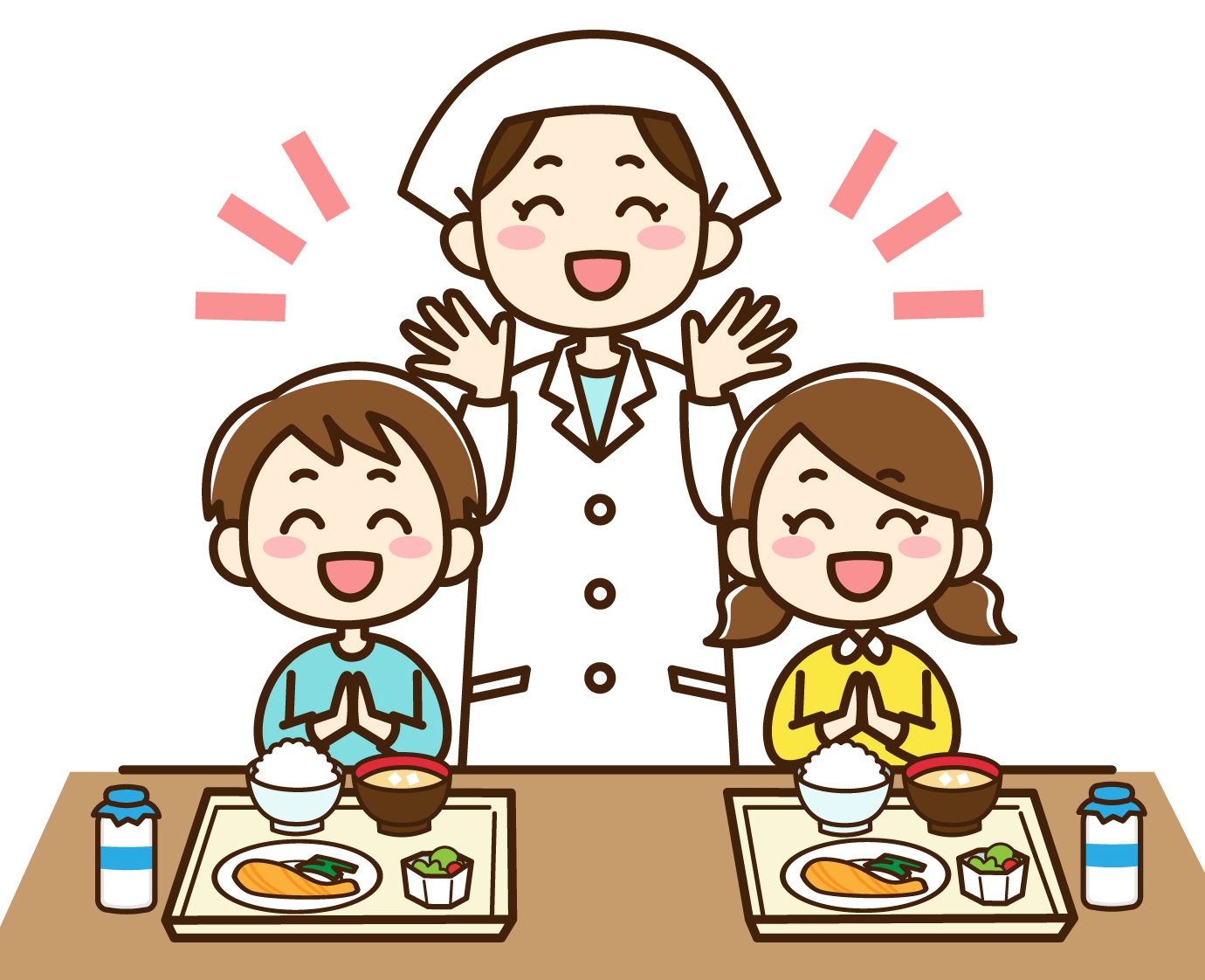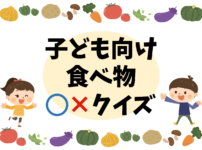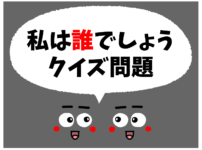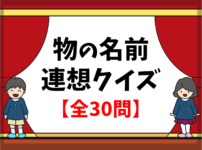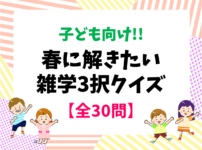王様
今回は給食3択クイズを出題するぞ!全問正解目指して頑張るのじゃ!
【給食クイズ】小学生に最適!食べ物おもしろ雑学3択問題【前編10問】
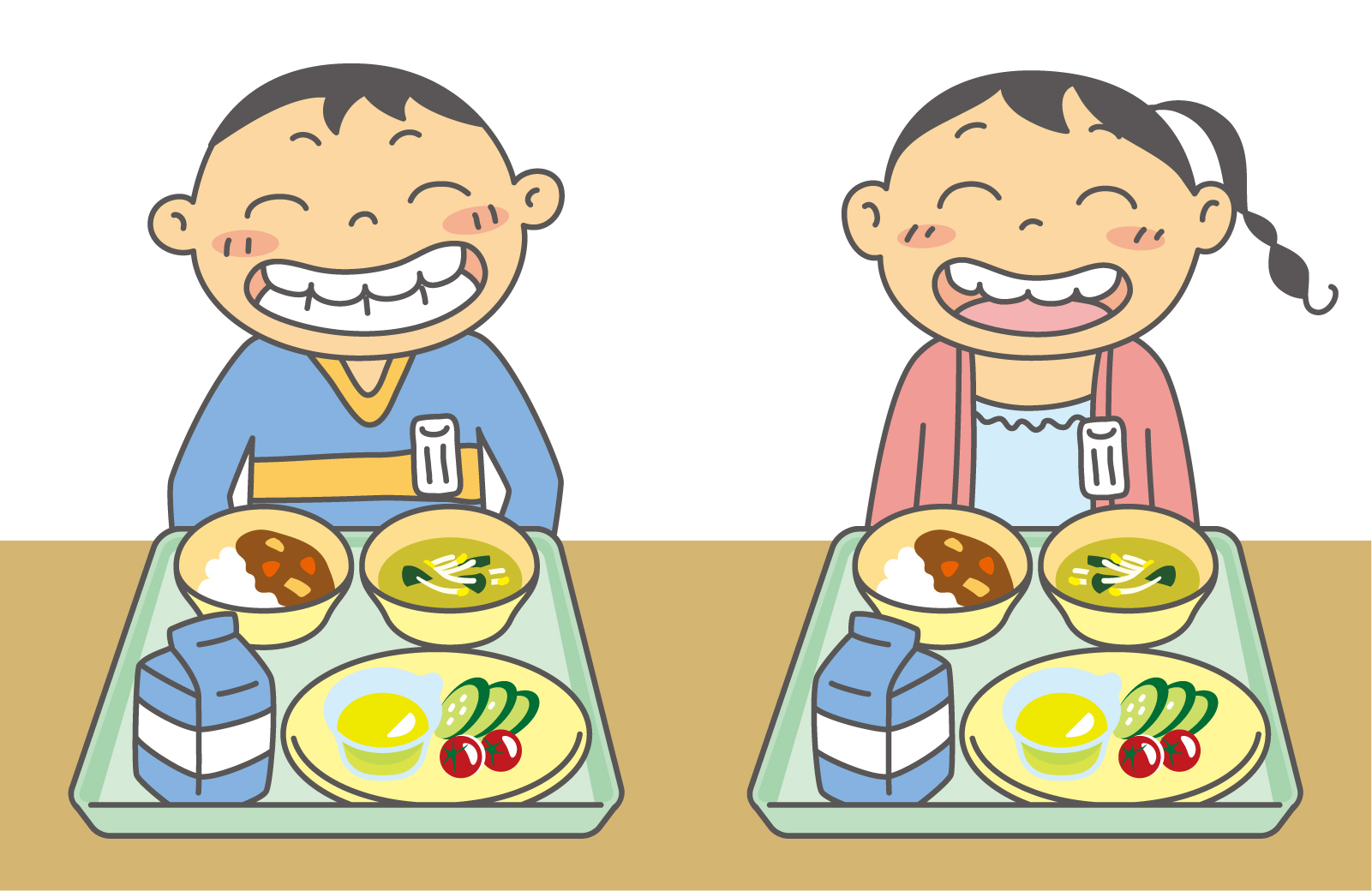

王様
まずは10問出題するぞぉ!選択肢の中から正解だと思うものを一つ選ぶのじゃ!
第1問
この中で実際に売られているカレーライスはどれでしょうか?
1.きゅうりカレー
2.いちごカレー
3.とうふカレー
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.いちごカレー
栃木県はいちごの名産地で、「いちごカレー」がレトルトカレーとして作られています。
見た目は普通のカレーにちょこっといちごが入っているものから、カレー自体がいちごをイメージしたピンク色になっているものまで様々です。
ぜひ見つけたらチャレンジしてみてください。
第2問
牛乳を温めるとある現象が起きます。
いったい何でしょうか?
1.膜ができる
2.泡立つ
3.匂いが強くなる
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.膜ができる
牛乳は40度以上に温めると表面に膜ができます。
温めると表面の水分が蒸発して、牛乳に入っているたんぱく質が固まることで膜ができるのです。
第3問
フルーツポンチの「ポンチ」とは元々どういう意味だったのでしょうか?
1.サラダ
2.デザート
3.お酒
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.お酒
元々「ポンチ」とはお酒をベースに砂糖や果汁を入れた飲み物でした。
そのお酒にフルーツを入れて楽しむものが「フルーツポンチ」でしたが、時代とともに「子どもも楽しめるように」と変化していきました。
その結果、アルコールが抜かれた今の形の「フルーツポンチ」が一般的になりました。
第4問
お菓子によくある「サラダ味」。
この「サラダ」とは何でしょうか?
1.野菜
2.ドレッシング
3.油
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.油
「サラダ味」とは「サラダ油」を使ったお菓子という意味です。
サラダ味のお菓子は基本的にサラダ油が使われて、味付けは塩味であることが多いです。
「サラダ味」のお菓子を食べても野菜の栄養は採れないので気をつけましょう。
第5問
揚げパンを初めて作ったのは誰でしょうか?
1.パン屋さん
2.学校の調理師さん
3.レストランのシェフ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.学校の調理師さん
揚げパンを初めて作ったのは、学校の給食を作っていた調理師さんです。
当時、風邪で休んでしまった子どもにパンを届けようと考えましたが、パンは時間が経つと固く美味しくなくなってしまいます。
「時間が経っても美味しいパン」を考えた結果、揚げて砂糖をまぶすことで「揚げパン」が誕生しました。
第6問
ピーマンが一番苦くなる食べ方はどれでしょうか?
1.丸ごと食べる
2.輪切りにする
3.みじん切りにする
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.みじん切りにする
ピーマンはたくさん切れば切るほど細胞が傷ついて、苦いもとの成分がたくさん出てきます。
したがって、細かく切り刻んでいるみじん切りは、一番苦みを感じやすい切り方となっています。
意外かもしれませんが、丸ごと食べるのが一番苦みを抑えやすいんです。
第7問
からあげにレモンが添えられている理由は何でしょうか?
1.茶色ばかりで見た目に華がないから
2.レモンをかけたほうがおいしく食べられるから
3.体に良いから
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.体に良いから
レモンをかけると胃腸の消化を良くしたり、脂肪が体に吸収されるのを防いだりしてくれます。
とは言っても食べすぎは良くないので気をつけましょう。
第8問
日本では食パンの外側は「耳」と呼ばれていますが、アメリカでは耳ではなく違う部位の名前で表されています。
いったい体のどこの部位でしょうか?
1.かた
2.かかと
3.くち
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.かかと
かかとは英語で「heel」と言います。
アメリカではパンの耳のことを「the heel of the bread(パンのかかと)」と呼びます。
パンの耳は固いことから、体の中で固い部位である「かかと」を使って表現しているのだそうです。
第9問
ドーナツに穴が開いている理由は何でしょうか?
1.食べやすくするため
2.生地代を節約するため
3.火が通りやすくなるため
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.火が通りやすくなるため
ドーナツに穴が開いている理由は、ドーナツの生地に火が通りやすくするためです。
実はドーナツは作られた当初は穴が開いていませんでした。
アメリカにドーナツの文化が来た時に、調理の時間を短くするために穴をあける方法を思いついたそうです。
第10問
お茶碗一杯にお米は何粒入っているでしょうか?
1.300粒
2.1000粒
3.3000粒
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.3000粒
お茶碗一杯(約150g)には約3000粒のお米が入っています。
【給食クイズ】小学生に最適!食べ物おもしろ雑学3択問題【中編10問】


王様
前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
新鮮な卵と腐った卵を見分けるには水に浮かべると分かるそうです。
このとき腐った卵は水に浮かべるとどうなるでしょうか?
1.水に浮く
2.水に沈む
3.水の中で立つ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.水に浮く
卵を水に入れると、新鮮な卵は中がしっかり詰まっているので水に沈みます。
古くなり腐った卵は、殻の細かい隙間から水分が蒸発して中身が少なくなり、さらにその隙間から空気が入っていることで水に浮きます。
卵の見分けがつかないときは、ぜひお家で試してみてください。
第12問
スイカを切るときに種が表面に現れない切り方はどれでしょうか?
1.黒い模様に沿って縦に切る
2.黒い模様をよけて縦に切る
3.横に切る
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.黒い模様をよけて縦に切る
スイカの種は中心から黒いしま模様の部分に向かって並んでいます。
そのため、黒い模様をよけるように包丁を入れると、切った断面には種が現れにくくなるんです。
第13問
ラーメンの好きな味ランキングの調査の結果、1位は「しょうゆ味」でした。
では2位は何味でしょうか?
1.しお
2.とんこつ
3.みそ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.みそ
ランキングの結果は「1位がしょうゆ、2位がみそ、3位がとんこつ」でした。
第14問
世界で一番たくさん作られている果物は何でしょうか?
1.りんご
2.ぶどう
3.ばなな
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ぶどう
世界中で育てられている果物のうちの4割がぶどうです。
すべてそのまま食べる用のぶどうというわけではなく、栽培されたぶどうのうち約8割はワインの材料として使われています。
第15問
この中で日本で生まれたパスタ料理はどれでしょうか?
1.ナポリタン
2.ミートソース
3.カルボナーラ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ナポリタン
基本的にパスタ料理はイタリアで生まれていますが、ナポリタンは日本で誕生しました。
戦後アメリカからケチャップが持ち込まれ、アメリカ軍の人たちがパスタにケチャップをかけただけの料理を食べているのを日本人のホテル料理長が見ていました。
「これではあまりにも味気ないし、栄養も少ない。」と感じたそうで、トマトやタマネギ、ピーマンなどを使用した今の形のナポリタンが完成し、これが美味しいと話題になって世間に広まっていきました。
第16問
栄養がたくさん入っている「納豆」。
この中で納豆の栄養が半減してしまう食べ方はどれでしょうか?
1.冷やして食べる
2.かき混ぜずに食べる
3.火を通して食べる
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.火を通して食べる
納豆に入っている「ナットウキナーゼ」という栄養は熱に弱いので、加熱したり熱々のごはんと混ぜて食べるとせっかくの大切な栄養素がしっかりと効果を出せなくなってしまいます。
栄養をちゃんと摂りたいときは、温めずに食べると良いでしょう。
第17問
シチューには主に「ビーフシチュー」と「クリームシチュー」があります。
日本で産まれたシチューはどちらでしょうか?
1.ビーフシチュー
2.クリームシチュー
3.どちらも日本で産まれた
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.クリームシチュー
ビーフシチューはフランスで誕生し日本に伝わってきました。
その後に日本で「給食で栄養が取りやすいように」と牛乳と小麦粉を入れた「クリームシチュー」が誕生して、その美味しさから家庭用にも広がっていきました。
第18問
果汁100%のジュースにしか許されていないパッケージに関するある決まりごとは何でしょうか?
1.果物の絵を使う
2.果物の写真を使う
3.果物の切り口を載せる
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.果物の切り口を載せる
果物の切り口(断面)のデザインをパッケージに載せていいのは、100%ジュースだけという決まりがあります。
ちなみに果物の絵は何%のジュースでも使用可能で、果物のリアルな写真は果汁5%以上でないと使えないという決まりもあります。
第19問
シュークリームの「シュー」はフランス語である食べ物が元となっています。
いったい何でしょうか?
1.トマト
2.キャベツ
3.ブロッコリー
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.キャベツ
フランス語で「シュー」は「キャベツ」という意味です。
シュークリームの膨らんだ見た目がキャベツに似ていることから「キャベツにクリームが入ったお菓子」ということで「シュークリーム」と名付けられたそうです。
第20問
お寿司の定番「イクラ」は、どこの国の言葉でしょうか?
1.ロシア
2.ポルトガル
3.日本
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ロシア
ロシア語で「魚の卵」や「小さいつぶつぶ」のことを「イクラ」と呼びます。これが、「イクラ」の名前の由来となっています。
ちなみに、ロシアでは魚の卵はすべて「イクラ」で表されるので、「イクラ」の前に色を付けて区別しています。
例えば、鮭の卵であれば「赤いイクラ」、キャビアであれば「黒いイクラ」といった感じです。
【給食クイズ】小学生に最適!食べ物おもしろ雑学3択問題【後編10問】
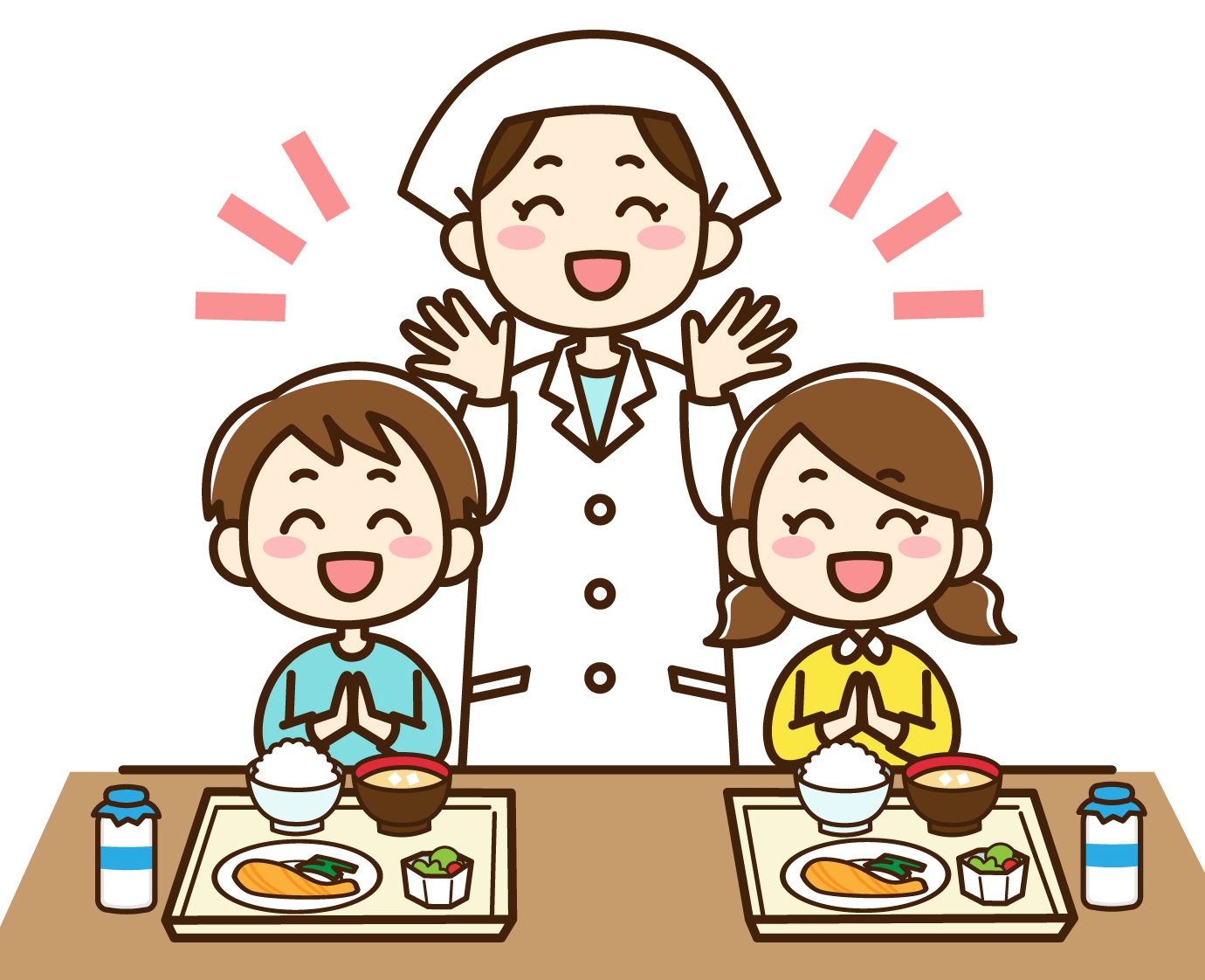

王様
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
学校給食に牛乳を出すように決めたのはだれでしょうか?
1.国
2.校長先生
3.給食センター
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.国
牛乳には子どもたちが成長するために大切なカルシウムなどの栄養がたくさん含まれています。
子どもたちに必要な栄養をとってもらうために、「学校給食法」という法律で学校給食に牛乳を出すように決められています。
第22問
とんこつラーメンのスープは何でダシを取っているでしょうか?
1.ニワトリの骨
2.ブタの骨
3.ウシの骨
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ブタの骨
「とんこつ」は漢字で書くと「豚骨」です。
つまり「ブタの骨」からダシを取っているということです。
第23問
次のうち、材料が牛乳ではないものはどれでしょうか?
1.バター
2.マーガリン
3.ヨーグルト
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.マーガリン
バターとヨーグルトは牛乳からできています。
マーガリンは牛乳ではなく、植物や動物の油からできています。
第24問
次のうち、ぬめりがあるキノコはどれでしょうか?
1.シイタケ
2.エノキ
3.ナメコ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.ナメコ
ナメコのぬめりは、ナメコが自分で出している成分です。
これで乾いてしまったり、虫に食べられてしまうのを防いでいるそうです。
第25問
今の納豆はパックに入っていますが、昔は何で包まれていたでしょうか?
1.わら
2.和紙
3.手ぬぐい
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.わら
納豆を作るためには「納豆菌(なっとうきん)」という菌が欠かせません。
納豆菌はわらの中にたくさん住んでいるため、わらが使われるようになりました。
今もわらで包まれた納豆があります。
第26問
次の中で実際にあるゴマの名前はどれでしょうか?
1.金ゴマ
2.銀ゴマ
3.銅ゴマ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.金ゴマ
ゴマは「白ゴマ」「黒ゴマ」「金ゴマ」の3種類にわけることができます。
第27問
「大学芋」の名前の由来はなんでしょうか?
1.大学の学食で初めて作られたから
2.大学生がよく食べていたから
3.大学生が考えたから
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.大学生がよく食べていたから
「大学芋」の名前の由来は、「大正時代から昭和時代の大学生がよく食べていたから」だと言われています。
その頃の大学生はお金がない人が多く、安くて美味しいサツマイモはありがたい食べ物だったそうです。
第28問
ヒジキは黒色の海藻(かいそう)というイメージですが、海の中で生えているヒジキは何色でしょうか?
1.黒色
2.白色
3.茶色
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.茶色
海の中に生えているヒジキは、茶色っぽい色をしています。
私たちが食べているヒジキは海で取った後にかわかしたもので、ヒジキはかわかすと黒色に変わります。
第29問
「よくかんで食べよう」と言われますが、何回くらいかめばいいでしょうか?
1.10回
2.20回
3.30回
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.30回
食事の時は、1口「30回」かむようにしてみましょう。
よくかむと「だ液」がたくさん出ます。だ液が多いと消化を助けてくれるので、栄養の吸収がよくなります。
また、だ液は口の中をきれいに保ち、むし歯の予防にもなります。
第30問
貧血の予防にぴったりな食べ物はどれでしょうか?
1.レバー
2.ほうれん草
3.納豆
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.レバー
貧血を予防するためには、「鉄分」を取ることが大切です。
鉄分は、レバーや赤身肉、ニワトリの卵やヒジキなどに多く含まれています。

王様
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
「クイズ王国」ではいろんなクイズを紹介しているから、他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!